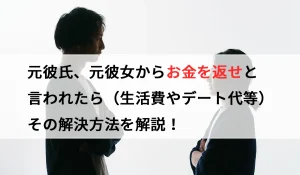この記事
の監修者
シン・イストワール法律事務所代表
田原 聡泰 弁護士

プロフィール閉じる
東京弁護士会所属
個人間の借金問題や、闇金問題、ホストの売掛問題、元恋人からの不当請求など違法な不当請求に対して10,000件以上の解決実績を持つ。お金を借りて困っている方、取り立てを受けて困っている方、通常の債務整理では対処できない問題の解決を得意としている。
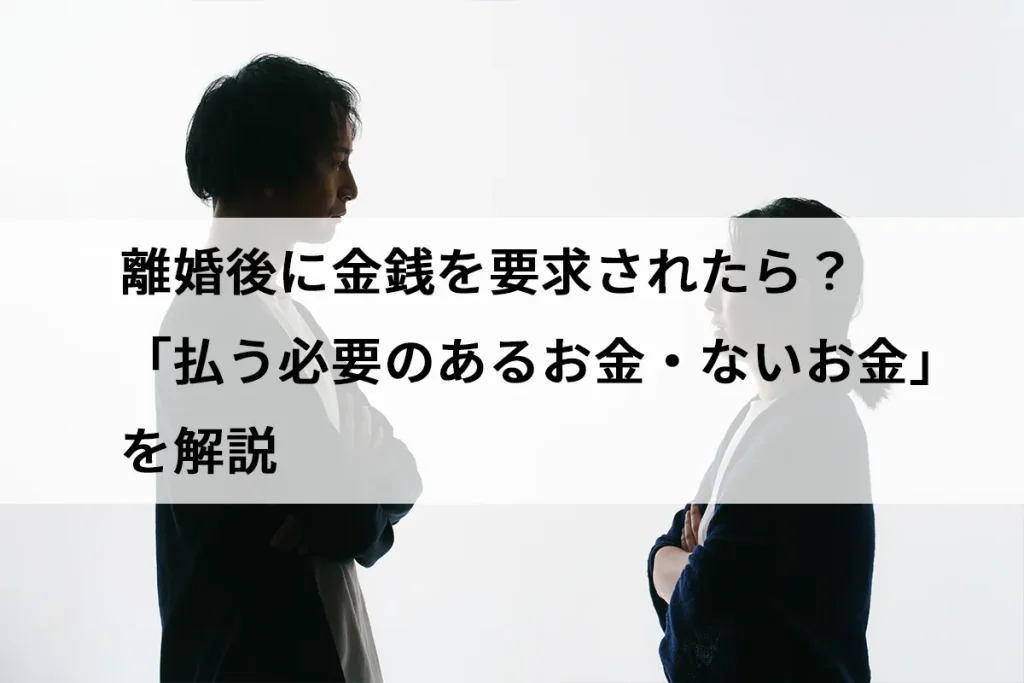
離婚が成立しても元配偶者との関係が完全に無くなる訳ではありません。離婚後に元配偶者から慰謝料や生活費などを請求されて「本当に払う必要があるの?」と頭を悩ませている方もいらっしゃるでしょう。
離婚後に金銭を請求された場合には、支払う必要のある金銭なのか、金額は適正なものなのかをしっかりと判断しなければなりません。
今回は、離婚後の金銭請求をテーマに、離婚後に金銭を請求される主なケース、支払う義務があるかどうかを判断するポイント、不当な請求への対処法などを解説します。離婚後の金銭請求への対応でお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。
男女間の借金の取り立て
不当な請求を最短即日ストップ
10,000件の解決実績!全国対応、相談無料

弁護士を通すことで
冷静に話がまとまります。
- 取り立ての最短即日ストップ
- 不当な金銭要求は支払い不要
- 払い過ぎたお金を返してもらう
- 減額やスケジュールの交渉
- 全国対応
- 無料相談
- 秘密厳守
ただいまのお時間はお電話がつながります!
離婚後に金銭を請求される主なケースとは?
離婚後に元配偶者から金銭を請求されるケースとしては、次のものが挙げられます。
- 財産分与
- 慰謝料
- 養育費
- 婚姻費用
- 年金分割
- 元配偶者間の貸金
- 生活費
ここでは、それぞれの金銭について、支払う義務があるのか、どのようなケースで請求されるのかを具体的に解説します。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻生活で協力して築き上げた財産を公平に分配する制度のことです。財産分与は、離婚時だけでなく離婚成立から2年以内であれば離婚後でも請求できます。
離婚時に財産分与の話し合いを行っていなかった場合、離婚後に財産分与の請求を受けることがあります。財産分与は、有責配偶者でも請求可能な権利です。そのため、相手に離婚の原因があるケースでも、財産分与の請求には応じる義務があります。
慰謝料
不貞行為やDV、モラハラなどが原因で離婚した場合、相手方に対して慰謝料を請求できます。離婚の慰謝料は、離婚成立から3年以内であれば請求可能です。
離婚時に慰謝料請求の原因がある場合でも、離婚の成立を急ぎたい、請求できることを知らなかったなどの事情で慰謝料の話し合いを行わずに離婚を成立させることがあります。このようなケースでも、離婚成立から3年以内(不貞行為の慰謝料は不貞に気付いてから3年以内)であれば、慰謝料を請求できます。
ただし、元配偶者から慰謝料を請求された場合でも、相手の請求にそのまま応じる必要はありません。相手方が主張する慰謝料請求の原因や金額については争う余地があります。
養育費
養育費の取り決めをせずに離婚した場合でも、子どもが20歳になるまでの間は元配偶者に対して養育費を請求できます。公正証書や調停調書で合意した養育費の支払いを怠っているケースでは、各支払日から5年以内であれば請求可能です。
養育費は子どもの健全な成長のために欠かせない費用です。元配偶者からの養育費請求には、応じる義務があります。
婚姻費用
婚姻費用とは、婚姻生活を営むうえで必要な費用のことで、夫婦は収入や資産に応じて婚姻費用を分担しなければなりません。離婚時に未払いの婚姻費用があった場合、離婚が成立した後でも婚姻費用の請求が可能です。
婚姻費用について公正証書や調停調書で取り決めをしていた場合、婚姻費用は支払期日から5年で時効となります。
婚姻費用についての取り決めをせずに離婚したケースでは、過去に遡って婚姻費用を請求可能です。ただし、離婚が成立するまでの期間や離婚後もしばらくは婚姻費用を請求していなかったという事実から、婚姻費用は必要なかったと判断される可能性も十分にあります。そのため、離婚後に婚姻費用を請求された際には、支払義務について争う余地があります。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金を分割して、それぞれが受け取れるようにする制度です。離婚時に年金分割の請求をしていなかった場合でも、離婚成立から2年以内であれば年金分割を請求できます。
元配偶者から年金分割の請求を受けた場合、離婚成立から2年以内であれば応じる義務があります。
元配偶者間の貸金
元配偶者間で金銭の貸し借りをしていた場合、離婚が成立したとしても貸金が無くなる訳ではありません。貸金の時効は、返済期日の翌日から10年間です。
元配偶者から貸金の返還を求められた場合、時効が成立していないのであれば支払いに応じる義務があります。
生活費
離婚後の生活費は、それぞれが負担すべきものです。元配偶者から生活費の支払いを求められたとしても、応じる義務はありません。
離婚後の生活費に困る状況になったなら、元配偶者に頼るのではなく転職して収入を増やす、親の支援を受ける、公的支援制度を利用するなど他の手段を検討すべきです。
支払う義務があるかどうかを判断するポイント
離婚後に元配偶者から支払いを請求された金銭について、支払う義務があるか否かを判断するポイントは、次の3つです。
- 離婚時に支払条件の取り決めをしていた金銭か否か
- 支払義務がある性質の金銭か否か
- 時効が成立しているか否か
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
離婚時に支払条件の取り決めをしていた金銭か否か
離婚時に支払条件の取り決めをしていた金銭のうち未払いのものは、時効が成立していない限り支払義務があります。ただし、養育費については、収入や家族状況の変化などに応じて金額を変更できる可能性はあるでしょう。
離婚時に支払条件の取り決めをしていなかった金銭については、金銭の性質によって支払い義務の有無を判断することになります。
支払義務がある性質の金銭か否か
離婚時に支払条件の取り決めがなかった場合でも、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用、年金分割については時効が成立していない限り、支払い義務があります。ただし、具体的な金額については相手の請求をそのまま受け入れる必要はなく、交渉や調停などで争うことが可能です。
元配偶者間の貸金については、離婚が成立した後でも返済条件に従って返済する義務があります。離婚後の生活費請求については、そもそも支払義務がありません。
時効が成立しているか否か
支払義務のある金銭であっても、時効が成立している場合には支払義務を免れます。それぞれの時効は、次のとおりです。
| 財産分与 | 離婚成立から2年 |
|---|---|
| 離婚慰謝料 | 離婚成立から3年 |
| 養育費 | 各支払期日から5年 |
| 婚姻費用 | 支払期日から5年 |
| 年金分割 | 離婚成立から2年 |
| 貸金 | 最後の返済日から10年 |
なお、不貞の慰謝料については、不貞行為の事実と相手方を知ってから3年で時効となります。また、養育費について取り決めがなかった場合には、子どもが20歳になるまで請求できます。
不当な請求への対処法
元配偶者から、支払義務のない金銭の支払いを請求されている、不当に高額な金銭の支払いを請求されているといった際の対処法としては、次のものが挙げられます。
- やり取りの証拠を残しておく
- 家庭裁判所の調停を利用する
- 弁護士に相談する
それぞれの内容について具体的に解説します。
やり取りの証拠を残しておく
元配偶者と金銭についての話し合いをする際は、メールやLINEなどでやり取りの証拠を残しておくようにしてください。口頭でのやり取りのみでは、言った言わないの話になり、争いが長引く可能性が高くなります。
また、支払条件について合意できた際には、合意書を作成しておくことも重要です。書面で支払条件を明確にしておけば、やり取りが蒸し返される心配もなくなります。
家庭裁判所の調停を利用する
元配偶者との話し合いでは解決せず不当な請求が続く場合には、家庭裁判所の調停を利用するのも有効な対処法です。
家庭裁判所の調停では、離婚後でも財産分与や慰謝料、養育費などの取り決めができます。当事者間での話し合いが進まないときでも、家庭裁判所の調停委員が仲介することで話し合いがまとまるケースは少なくありません。
当事者間での解決が難しいと感じたときには、家庭裁判所の利用を検討してみてください。
弁護士に相談する
元配偶者からの不当な金銭請求にお悩みの方は、弁護士への相談がおすすめです。
そもそも、相手からの請求が不当なものであるか否かを判断するには、専門的知識と経験がなくてはなりません。弁護士に相談すると、具体的な状況から、支払義務があるのか、金額は適切なものであるかについて適切な判断をしてもらえます。
さらに、弁護士に手続きを依頼すると、元配偶者との交渉や家庭裁判所での調停などを任せられます。元配偶者との金銭問題を自分自身で解決しようとすると、時間や手間がかかるだけでなく精神的にも大きなストレスを抱えることになるでしょう。弁護士に手続きを任せると、手間や時間、精神的ストレスからも解放されます。
離婚後の金銭請求についてよくある質問
ここでは、離婚後の金銭請求のよくある質問について簡潔に回答します。
離婚から5年経って請求されたが、支払う必要ある?
離婚から5年経っても支払に応じる義務があるか否かは、離婚時に支払条件の取り決めをしていたか、金銭の性質は何かによって異なります。離婚時に取り決めをしていなかった財産分与や年金分割などを離婚から5年経って請求されても、支払う必要はありません。一方、取り決めをしていなかった養育費については、子どもが20歳になるまで支払い義務があります。
元配偶者がしつこく連絡してくるが、どうすれば?
当事者同士での話し合いでは納得してくれない場合には、家庭裁判所の調停を利用する、弁護士に相談するなどの対処法を検討してみてください。
子どもがいない場合でも養育費以外の請求はある?
子どもがいない場合でも、養育費以外の請求を受ける可能性はあります。たとえば、財産分与や慰謝料、年金分割などは、離婚が成立してからでも請求可能です。
まとめ
離婚後であっても元配偶者から金銭を請求されることはあります。元配偶者の請求に応じるべきかは、支払義務がある性質の金銭か否か、時効が成立しているか否かなどから判断しなければなりません。
相手の請求に応じる義務があるのか、金額が適切かについてお悩みの方は、弁護士への相談がおすすめです。シン・イストワール法律事務所では、無料相談を実施しています。離婚問題について解決実績豊富な弁護士が対応させていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
男女間の借金の取り立て
不当な請求を最短即日ストップ
10,000件の解決実績!全国対応、相談無料

弁護士を通すことで
冷静に話がまとまります。
- 取り立ての最短即日ストップ
- 不当な金銭要求は支払い不要
- 払い過ぎたお金を返してもらう
- 減額やスケジュールの交渉
- 全国対応
- 無料相談
- 秘密厳守
ただいまのお時間はお電話がつながります!